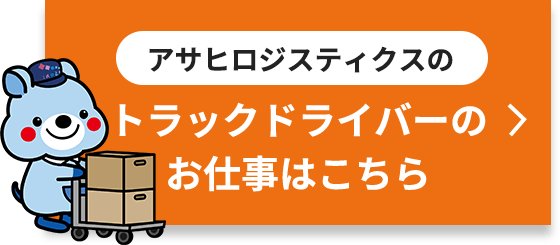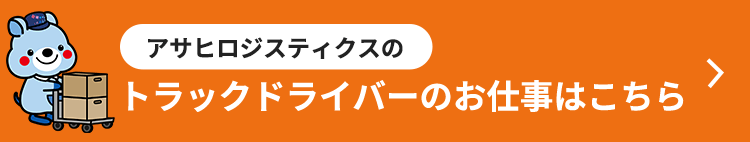3温度帯とは
3温度帯とは、物流業界において荷物を保管・運送する際の適切な温度を示す用語であり、常温(ドライ)・冷蔵(チルド)・冷凍(フローズン)の三つの区分からなります。なお、生鮮食品を扱う業者の場合、より厳密な温度管理が必要となるため、三温帯にパーシャルと氷温を加えたさらに細かい区分を使用するのが一般的です。
3温度帯それぞれの温度
3温度帯のそれぞれに対応する温度には、厳密な定義があるわけではありません。ですが、一般的には、次のような基準が広く用いられています。
- 常温:10~15℃
- 冷蔵:5~マイナス5℃
- 冷凍:マイナス15℃以下
さらに、生鮮食品を扱う業者が使用する区分を付け足すと、次のようになります。
- 氷温:0~マイナス3℃
- パーシャル:マイナス3℃
また、三温帯とは別に、倉庫業法で厳密に基準が定められた区分として、次のような区分があります。
- C3級:0~10℃
- C2級:0~マイナス10℃
- C1級:マイナス10~マイナス20℃
- 調理用冷凍食品:マイナス18℃
- F1級:マイナス20~マイナス30℃
- F2級:マイナス30〜マイナス40℃
- 超冷凍・F3級:マイナス40~マイナス50℃
- F4級:マイナス50℃以下
参照元:株式会社関通「3温度帯とは」(https://www.kantsu.com/terms/3330/)
温度帯ごとの倉庫の特徴
常温倉庫
冷却設備をもたない一般的な倉庫は常温倉庫となります。季節によって温度が変わるため、生鮮食品等を保存することはできませんが、その分リーズナブルに維持することができる倉庫です。
冷蔵倉庫
庫内温度が10℃以下となる冷蔵倉庫は、主に生鮮食品を保管するために使われます。なお、10℃以下の温度を保ちながら荷物を保管および輸送・配達することを冷蔵物流業界と呼びます。
冷凍倉庫
庫内温度がマイナス18℃の倉庫を冷凍倉庫と呼び、冷凍食品や冷凍された食肉および魚介類等の保管のために使用されます。冷凍食品のニーズが高まるにつれて、需要も大きくなっている冷凍倉庫ですが、維持費が高いことから、まだまだ数が少ない倉庫です。
まとめ
3温帯は、食品を取り扱う企業にとって特に非常に重要な区別です。自社商品にとって適切な温度はどれなのか、間違った倉庫を使用することで無駄なコストが発生していないか等について、三温帯の区分を踏まえながら、普段からしっかりと確認・把握しておくようにしましょう。
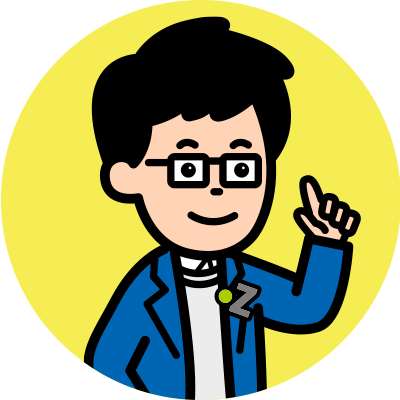
3温度帯の管理の難しさや維持費の高さから小さい企業ではなかなか行えます。一方でここの管理や維持ができている企業は大きな企業として安定していると言えます。このメディアでは食品配送ドライバーの世界について紹介しています。興味のある方はぜひご覧ください。